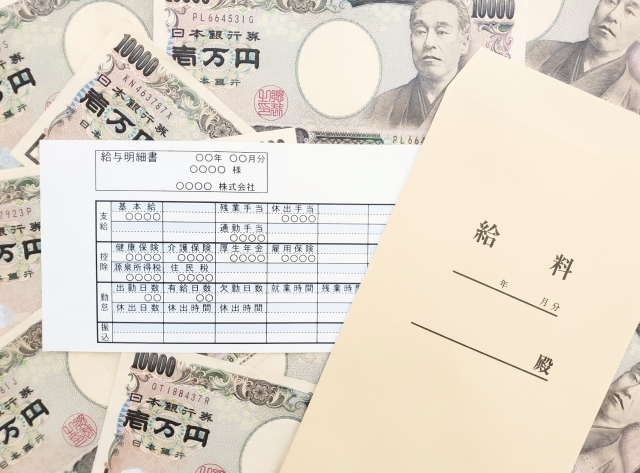「部下がぜんぜん動かないんだよなあ」
「指示しないと何もやらない」こんな上司のつぶやきが聞こえてきます。
それ、もしかすると給料の15%をムダにしているかもしれません。
冗談ではなく、実際に企業で「指示待ち社員」が増えると、生産性が目に見えて落ち、
人件費の15%前後がムダに消えているというデータもあるのです。
「指示待ち社員」が生む“静かな損失”
たとえば、月給30万円の社員が「自分で考えず、言われたことしかやらない」状態だったとします。
一見、仕事はしているようでも、実はその多くの時間が「待機モード」。
自ら課題を見つけて改善したり、新しい提案をしたりはしなません。いわば“半分さぼり”状態です。
この「指示待ち時間」が全労働時間の15%だとしたら、それは月に4万5千円分の給与がムダになっているということ。年にすれば54万円、社員10人いれば540万円の損失です。
しかもこのコストは「見えにくい」。
製造ラインの停止は気づけても、「人の業務待機」「人の思考停止」には気づきにくいのが厄介なところなのです。
なぜ、指示待ち社員が生まれてしまうのか?
では、なぜこうした「指示待ち社員」が生まれてしまうのでしょうか?
理由はさまざまありますが、共通して見られるのが以下のような要因です:
- 上司が細かく指示しすぎている
→ 上司のやり方を押しつけているため、部下は指示以外は動けません。 - 経営理念やビジョンが浸透していない
→ 何を判断軸にしていいか分からないため、自信を持って行動できません。 - 減点主義の空気
「失敗=叱責」「前例踏襲が安全」という学習が染みつくと、人は“動かない”ことで身を守ります。 - 「考えること」を求められてこなかった文化
→ 考える前に「指示を仰ぐ」が当たり前になります。 - 評価が“言われた通り”を褒める
創意工夫より遵守が高評価。そりゃ工夫しなくなります。
つまり、指示待ち社員は“育ってしまった”のであって、もともとそういう性質だったわけではありません。
「考える力」を封じられた結果、組織がそういう人を生んでいるのです。
「任せる力」が組織を変える
指示待ち社員を脱却させるカギは、実は「上司の側」にあります。
それは、部下に「権限」をきちんと委譲することです。
たとえば、こういう関わり方です:
- 「目的」は上司が示す
- 「やり方」は部下に考えさせる
- 成果については部下自身が振り返り、評価する
このプロセスを習慣にすることで、部下は「任された感」を得て、徐々に自律的に動けるようになります。
最初は時間がかかるかもしれませんが、結果的に上司の負担も減り、チーム全体のスピードが上がるのです。
経営理念が羅針盤になる
ただし、これを成功させるためには前提があります。
それは、社員一人ひとりが「何のために仕事をしているのか」=経営理念やビジョンに共感し、理解していることです。
目的地が共有されていない状態で「自由にやっていい」と言われても、誰も自信を持って動けません。
だからこそ、まずはトップが自らの思いを言葉にし、社員と共有し続ける必要があります。
「うちは理念なんて掲げてないよ」とおっしゃる社長も、少なからずいらっしゃいます。
でも、社員が動かない原因は、その“羅針盤の不在”かもしれません。
指示待ち文化を変えるなら、まずはリーダーから
組織が変わるには、まずは「上司自身」が変わること。
「なんでうちの社員は動かないんだ?」と嘆く前に、
「私は部下に“任せる”ことができているだろうか?」と問い直してみてください。
そして、その変化の第一歩としておすすめしたいのが、『自律型組織構築セミナー』です。
このセミナーでは、指示命令型マネジメントではなく、社員が自ら考え、動く組織をどう作るかについて10年をを超える実績から実践的に学べます。
「また今日も部下にイライラして終わった」
そんな毎日から抜け出したい経営者の方に、ぜひ体験していただきたい内容です。
まとめ:15%のムダを、投資に
それ、指示待ち社員は、“社員の問題”ですか?
もしかすると、あなたの会社に眠っているのは、ムダな人件費ではなく、「まだ開花していない可能性」かもしれません。
指示待ち社員は、伸びしろのかたまりです。
“待ち”を“動き”に変えるのは、上司であり、組織文化であり、経営のあり方です。
指示待ち社員の無駄なコストを投資に回してみませんか?
自律型組織づくりは根性論ではなく“技術”です。
会議設計、評価設計、委譲の段階設計、理念の理解・共感——いずれも10年以上の経験からの知見であり、再現性があります。
指示待ち社員から自律型社員に変えて行きたいのであれば、まずは「自律型組織構築セミナー」への参加をお勧めます。
これが、指示待ち社員”無駄なコストの15%を取り戻す最短ルートです。